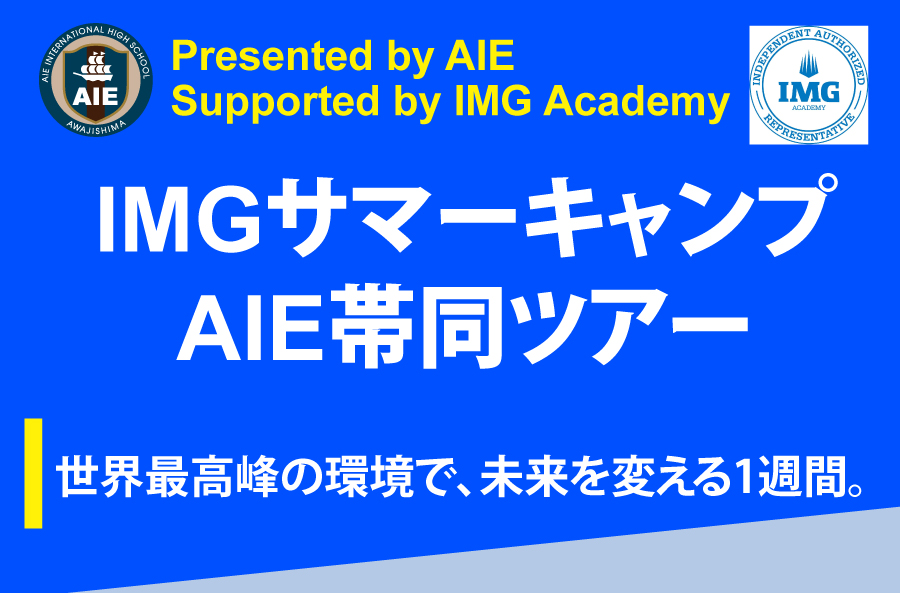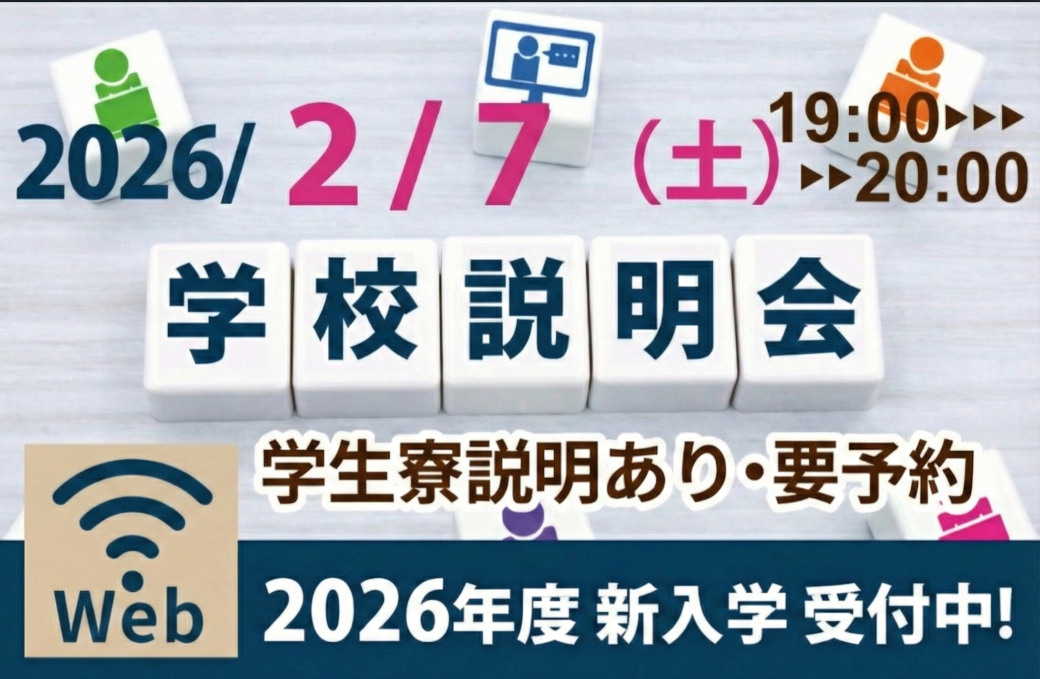今回は、イギリスの名門サセックス大学で国際開発学を学ぶ、卒業生の松島さんにお話を伺いました。高校時代から海外留学を視野に入れ、自ら道を切り拓いてきた松島さん。なぜ国際開発学に興味を持ったのか、そして世界的に評価の高いサセックス大学へはどのように進学したのか。その決断の裏側にある想いや、現在の学び、将来の展望について語っていただきました。

- 松島リサさん(高校在籍中はオンラインコース・通信コースに在籍)
高校卒業後、イギリスのサセックス大学へ進学。国際開発学部(International Development)に在籍。アルバイトでの経験をきっかけにフードロス問題に関心を持ち、文系の視点から社会問題を学ぶべく、同大学で学んでいる。
今、学んでいることと、そのきっかけ
―― まず、サセックス大学ではどのようなことを学んでいるのか教えてください。
サセックス大学の国際開発学部で学んでいます。学科という形ではなく、国際開発学という大きな枠組みの中で、自分の興味に合わせて様々なモジュール(科目)を選択するスタイルです。
今学期は、「環境学から見る国際開発」「エネルギー革命について」「国家の発展」といった政治的なテーマの授業や、デモやキャンペーン活動がどのように成り立っているのかを分析する授業などを履修しています。
―― 国際開発学、特に環境問題に興味を持ったきっかけは何だったのでしょうか?
もともと環境問題に興味があり、その原点は学生時代のお菓子工場のアルバイト経験です。商品を大量生産する工場だったのですが、決まった時間に大量のケーキの材料が廃棄されるのを目の当たりにしました。まだ食べられる、商品になりうるものが捨てられていく光景に衝撃を受け、「このような問題が他にもあるのではないか」と考えるようになったのがきっかけです。
当初は「環境学」を学びたいと考えていましたが、多くの大学では理系の側面が強く、私は社会問題として文系の視点からアプローチしたいと思っていました。環境問題だけでなく、地球上で起きている様々な問題に広く興味があったので、分野を絞らずに学べる学部を探し始め、そこで「国際開発学」に出会いました。「これだ!」と思いましたね。
―― なぜ、数ある大学の中からサセックス大学を選んだのですか?
実は、国際開発学という学問はイギリスが起源で、研究が非常に進んでいます。その中でもサセックス大学は、この分野で世界トップクラスの評価を得ていました。
高校生の時にイギリスのブライトンという街に語学留学した経験があるのですが、正直に言うと、当時は「もう一度住みたい」と思えるほど良い思い出ばかりではありませんでした。しかし、自分の学びたいことが明確になった時、過去の好き嫌いでチャンスを逃すのはもったいない、と。学問を突き詰めるために大学に行くのだから、その分野で一番強いところに行こうと決意し、サセックス大学を選びました。
独自の入学プロセスとIELTS攻略法
―― イギリスの大学、しかもトップクラスとなると入学試験も大変だったのではないでしょうか。
それが、少し特殊なルートなんです。サセックス大学には「インターナショナル・イヤー・ワン」という、大学が提携する教育機関が提供するプログラムがあります。これは大学準備コース(ファンデーションコース)と大学1年次の内容が一体化したもので、このコースに入るために必要だったのが、高校の成績とIELTSのスコア(5.5)でした。面接や小論文はなかったんです。
この1年間のプログラムを規定の成績以上で修了すると、サセックス大学の正規の2年生として編入できる仕組みになっています。編入の際も特別な試験はなく、コース内の課題の成績で判断されます。
―― IELTSのスコアアップのために、どのような勉強をしましたか?
語学学校に通ったことが大きいですが、アカデミックな文章力は自主的に勉強しないと伸びません。問題集を繰り返し解いたり、学術的な単語を重点的に覚えたりしました。また、無料で使える過去問アプリなども活用していましたね。日々の会話力だけでなく、試験に特化した対策が重要だと思います。
多様な価値観に触れる大学生活と、学びを支える力
―― 実際にサセックス大学で学んでみて、いかがですか?
松島さん: 本当に来て良かったと感じています。世界トップレベルの研究環境はもちろんですが、世界中から留学生が集まっているので、多様な価値観に触れられるのがとても刺激的です。同じ国際開発学という分野でも、私のように環境問題を切り口にしている学生もいれば、教育に関心がある学生もいる。幅広い学問だからこそ、様々な思想を持った仲間と出会えるのが最大の魅力ですね。
課外活動では、1年目にはキャンパス内のリサイクルを推進する「サステナビリティ・ソサエティ」に、2年目からは新しいことに挑戦したいと思い、「ゴルフ・ソサエティ」に所属しています(笑)。
―― 現在の学びを支えている、高校時代の経験などはありますか?
高校時代に受けた授業で「勉強の方法そのものを学ぶ(Study Skills)」という経験をしたことが、今すごく役に立っています。「勉強のための環境を整える」といった、学習の前提となる考え方やスキルを体系的に学ぶ機会は、それまでありませんでした。どうすれば効率的に学べるかという根本的なスキルが、大学での主体的な学習の大きな土台になっていると感じます。
将来の夢と後輩たちへのメッセージ
―― 卒業後の進路については、どのように考えていますか?
当初はイギリスでの就職も考えていましたが、国際開発学の分野でキャリアを築くには大学院への進学が一般的だと知りました。国連やNGOなどで働く道もありますが、私の原点であるフードロス問題を考えると、個人や団体の活動よりも、ビジネスの仕組みそのものを変えるアプローチがしたいという想いが強いです。問題を生み出している企業の中から社会を変えていく、ということに挑戦したいので、今は日本での就職を視野に入れ、活動を始めたところです。
―― 最後に、進路に悩む後輩たちへメッセージをお願いします。
私自身も今、就職活動で悩んでいる最中なので偉そうなことは言えませんが、「遠い将来を見据えすぎず、今やりたいことで選ぶ」のが良いと思います。
母からもよく言われるのですが、人生は思っているようには進まないし、状況は常に変わるものです。「将来のため」と考えて選んだ道も、自分のモチベーションが続くとは限りません。それよりも、「好き」と思えることがあるなら、それは一つの才能です。その気持ちを大切に、伸ばしていく方が結果的に楽しく、将来にも自然に繋がっていくのではないでしょうか。
少しでもワクワクするな、と感じる方へ、思い切って一歩踏み出してみてください。
松島さん、この度はインタビューにご協力いただき、本当にありがとうございました!
アルバイトという身近な経験からフードロス問題に関心を持ち、自らの意志で道を切り拓いて、世界トップクラスのサセックス大学で学んでいるお話に、深く引き込まれました。
「『好き』という気持ちを大切にして 」という後輩へのメッセージは、進路に悩む多くの学生たちの背中を力強く押してくれるはずです。
日本での就職活動、そしてその先の夢の実現を、心から応援しています!今回は、勇気の出るお話をたくさん聞かせていただき、本当にありがとうございました。